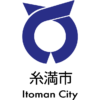沖縄戦跡慰霊巡拝の記録「その4」となります。
その3は、下記にて。
2022年10月記録です
「ひめゆりの塔」は、伊原第三外科壕の跡地。
ちかくには、同じように南部に追い込まれてきた陸軍病院本部壕と、伊原第一外科壕、伊原第二外科壕などもあった

みたま安らかに
目次
沖縄陸軍病院
昭和19年6月、開南中学に開設したことに始まる。
南風原に移転したのちに、昭和20年5月下旬、南部に分散移転し、伊原の近くの山城集落の「山城壕」が本部となった。6月18日に解散した。
沖縄陸軍病院之塔
沖縄陸軍病院之塔
この塔は戦没された沖縄陸軍病院の傷病将兵及び職員と学徒の慰霊塔である
慰霊会(遺族及び戦友の会)が昭和39年1月26日に建立し平成4年6月23日これを再建す

春くると ひたすら待ちし 若草の 萌え立ついのち 君は捧げぬ
水汲みに 行きし看護師 死ににけり 患者の水筒 四つ持ちしまま
陸軍病院の軍医であった長田紀春氏が詠んだ歌碑。

ひめゆり学徒隊(沖縄師範学校女子部・沖縄県立第一高等女学校)
沖縄師範学校女子部の前身は、1886年(明治19年)に師範学校内に設置された「女子講習科」でした。その後変遷を経て、1943年(昭和18年)に国立の専門学校に昇格し、「沖縄師範学校女子部」に名称を変更しました。
沖縄県立第一高等女学校の前身は1900年(明治33年)に設置された「市立高等女学校」でした。1928年(昭和3年)に「沖縄県立第一高等女学校」に名称を変更しました。
1945年(昭和20年)3月23日、学徒たちに動員命令が下され、配置先の沖縄陸軍病院があった南風原に向かいました。
4月中旬~下旬、戦況悪化による負傷兵の増加に対応するため、一日橋分室、識名分室、糸数分室が設置され、学徒たちも配置されました。
5月下旬、米軍は首里戦線へ侵攻を開始し、日本軍は南部への撤退の準備を始めました。25日には、沖縄陸軍病院にも撤退命令が下されました。
26日に学徒らは井原に到着し、翌27日、山城、波平、糸洲、井原の壕へ分散配置されました。
6月18日、学徒らは学徒隊の解散命令を受けました。米軍のg猛攻撃の中、負傷した学徒は壕に残され、壕を出た学徒たちは、砲弾が飛び交う中、逃げ惑い、追い詰められ、多くの命が失われました。
平成28年3月 沖縄県子ども生活福祉部保護・援護課

沖縄陸軍病院山城本部壕(山城本部壕)
地元ではサキアブと呼ばれる自然洞穴です。すり鉢状の窪地部分から中に入ると、壕口のある広場と奥の広場の2つに分かれています。
1945年3月、米軍の猛爆撃や艦砲射撃が始まると、山城の住民の一部がこのサキアブに避難しました。
5月下旬、南風原にあった陸軍病院が南部に撤退し、この場所を病院本部壕として、第一外科壕、第三外科壕を井原に、第二外科壕を糸洲におきました。陸軍病院には、沖縄師範女子部と県立第一高等女学校の学徒も配属されていました。廣池文吉病院長以下の首脳陣らは、伝令や命令受領者を通じ、分散した各外科壕を統率しましたが、撤退後は病院としての機能はほとんど失われていました。
6月14日、本部壕入口付近に落ちた直撃弾によって、廣池文吉病院長をはじめとする兵士や学徒の多くが戦死または負傷しました。6月18日、沖縄陸軍病院は解散となり、病院勤務者や学徒らは、米軍の激しい包囲攻撃の中をさまようことになりました。
糸満市 平成31年3月


下に降りることができる。


合掌





場所:
位置関係
陸軍病院本部壕と第一外科壕・第二外科壕・第三外科壕の位置関係

第一外科壕
第三外科壕(ひめゆりの塔)の近く。



碑文。
くずし字で非常に難解。。。
ここは陸軍病院第一外科及び糸数分室所属の軍医看護婦、沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校職員生徒のいた壕である
米軍の迫まる1945年 6月18日夜、軍より学徒隊は解散を命ぜられて、弾雨の中をさまよい照屋秀夫教授以下多くはついに消息をたった
軍医看護婦患者も同じく死線を行く生死のわかれの地点である
ここで負傷戦没した生徒
(犠牲者の氏名省略)
藤野憲夫沖縄県立第一中学校長もここで最後を遂げられた
謹んで記して御冥福を祈り平和を祈願する
しらじらと 明けそむる野を 砲弾の
雨に散りゆく 姿目に見ゆ
血にそまる 巌のしづくは 地底にしみて
命の泉と 湧きて出でなむ
1974年 6月 ひめゆり同窓会





場所:
※撮影:2022年10月
沖縄戦跡慰霊巡拝
「その5」へ